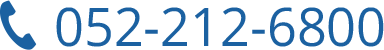8.忌み数の話
日本人にとって4、四(死)という数字は、キリスト教の13にあたる忌み数字。
単なる語呂合わせ程度なのに、駐車場に4番はなく、飛行機でも日本の航空会社でボーデング番号に4番はない。4番の席だけ落ちることはないのに。
病院にも4号室はない。
語呂合わせで、4を死に結び付けたがる日本人のなんと多いことか。
では、何故カレンダーから4月を除かなかったのか。語呂合わせだから日本だけの現象だ。
最近のコインパ-キングには、4番が出てきている。
“病院が語呂合わせの迷信を信じるわけにはいかない。”
そのうち、最先端医療を自負している病院には、語呂合わせの迷信をやめて4号室、14号室のある病院が出てくるだろう。
そうなればひょっとすると、患者の親族、特に奥様からの強い要望で、4病棟の4号室は予約で一杯になるかもしれない。予約が取れない客から、”他の病室は空いているのに、何故、4号室だけが抽選なのだ!“とカスハラで受付が滞ってしまいそうだ。四号室を設けたら、想像の世界だが実際にどうなるだろう。
病院に対応策はないのかと聞くと、”4号室は一つしかありません”と事務的な答えが返ってくる。聞くと、その理由はきっと不明だとしか言わないだろう。
外国のホテルには420号室はない。4月20日はマリファナ国際記念日(マリファナ・デ-)の日であり、「フォ-・トゥエンティ-」という。
この日の4時20分は、世界の大麻愛好者が集まり、大麻を吸って大麻の合法化を訴えるイベントが行われる。
420号室で大麻の煙を充満させられては、ホテル側はたまらない。だから420号室を無くしてしまった。
カナダのバンクーバー、イギリスのロンドン・マンチェスターは、公園で「マリファナ・フェスティバル」が開かれる。
1970年代、カリフォルニアのサン・ラファエル高校の生徒たちが、放課後の午後4時20分に、ルイ・パストゥールの銅像の前に集合して、大麻を吸っていたことが切掛けとなったようだ。
フォー・トゥエンティーは、大麻の隠語である。
死は、誰にでも訪れるから怖いので「四」を避けたい。
しかし、死がなかったら、全身老化と故障で、痛みと苦痛を永遠に味わうことになる。この世で永遠の地獄を味わいたくない。死がそれを解決してくれると思えばむしろ歓迎すべきこと。
でも、奥様方はそこまで考えて、4号室を予約するだろうか?
4号室は「患者本人のためなのか、遺族のためなのか」と病院に聞けば、患者次第だという回答になる。
病気になったら患者本人の意思を大事にしよう!
えっ!
もう手遅れ?
9.沈黙の人種差別の話
戦争直後、米軍による進駐軍の多くの家庭に、日本人がメイドとして雇われた。
メイドが男であれ女であれ、進駐軍の家族達はメイドの前で素っ裸になってシャワ-をあびる。メイドの前で素っ裸になるのに何ら抵抗感がない。犬や猫の前で裸になっても恥ずかしくないのと同じで、日本人を人間だと思っていなかった。という誠らしき噂が当時あった。
しかし、バンザイ岬や沖縄で、米軍に包囲された日本人の女性が、レイプを恐れて崖から飛び降りて死んだ。あれは、日本人の勝手な妄想だったのか。
満州では、日本人の女性の多くがソ連兵にレイプされたという。
戦後、日本がアメリカの占領下にあったとき、米軍相手の売春婦がいた。
どうも日本人を性の対象としてみなかったというこの話は、眉唾物だったのではないか。これが逆なら絶対嘘だと解かるが、いかにも真実のように聞こえる。沈黙の差別を受け入れる深層心理が、白人に対するコンプレックスのようなものが関わっている気がする。
10.トランスジェンダーの話
LGBTQは最近の現象ではない。
明治以前、男色は結構いたようだ。
後白河天皇の愛人は藤原信頼だった。天皇が男色だとその者へ異例の出世をさせたことで解る。江戸時代の宿場町では、男性相手の男郎部屋があったことからも解る。
織田信長は有名であるが、徳川綱吉も男色であった。
江戸の町は、男性が女性の1.7倍いた。男女比が平等になるのは明治以降で、男色がタブ-となったのは明治の西洋文化(キリスト教文化)の影響である。
天秤棒で、糞尿が入った樽を担いだ屈強の男に惚れた男がいた。
三島由紀夫である。彼は幼少の頃に男色の傾向があることに気づいていた。
彼が偉大な作家として世に知られるようになったのは、多分に自ら男色を否定する心の葛藤が、エンジンになったのではないだろうか。
クリスチャンが殆どいない日本で、LGBTQを差別するのは日本の伝統文化の否定である。
2024年4月1日、スコットランドで「ヘイトクライム法」が施行された。
この国でレイプ犯「アイラ・ブライソン」が有罪判決を受けたが、女性自認しているので女性刑務所に入れるか否かで当局は迷った。スコットランドでは、すでに女性自認している男性に対し女性刑務所に送還されている例がある。
議会は男女の区別をすること自体差別としているが、女性刑務所に入りたくてレイプする悪質な人間が後を絶たない。
本当のトランスジェンダーはレイプの常習犯にはならないが、外見で見分けがつきにくい。
女性専用列車、女子トイレは何の意味も持たなくなる。
ところが、ハリーポッターの主役である「ダニエル・ラドクリフ」氏は、ハリーポッターの著者「Kローリング」氏と対立している。
この2人の対立は、世論を二分する政治論争になっている。
2015年のIOCの規則では、男性ホルモンのテストステロン値が、1リットル当たり10ナノ未満であれば、”私は女性よ!“として出場可能としている。
アメリカの大学は、トランスジェンダーが女子の運動部に参加することを禁じている。スポーツはイデオロギーではなく、生物学を土台にするという方針。
アメリカはゲイが多く、これに真っ向から反対している。
女子テニスのレジェンド「マルチナ・ナブラチロワ」は、女性とトランスジェンダーを競わせるのはインチキだと、新聞のコラムに書いたことで批判を受けた。
女子スポーツは存在しなくなるのを恐れての発言だった。
トランスジェンダーの権利主張がスポーツの世界でなく、女性専用列車や女子トイレ、女性専用浴場、女子刑務所に及ぶと社会はより複雑になる。
動物行動学者の「竹内久美子氏」によれば、”同性愛者は遺伝的なもので、人口調整のために遺伝に組み込まれている”という。
多産系の家系に特有な現象で、女性ホルモンが多い家系の場合はホモが多く、男性ホルモンが多い家系の場合は、レズが生まれる確率が高いのだそうだ。ホモの脳は「女性脳」だから、女性よりも女性らしくなる。女性ホルモン過多の男性である。
要は人口爆発が起きないよう、調整機能遺伝子がLGBTを生んだのだ。
当事者はそっとしておいて欲しいのに、こういう人を政治利用する社会に問題があるような気がする。
11.夫婦別姓の話
3~4世紀の古墳の埋葬者は男女の割合が半々だった。この男女は夫婦ではない。男性優位になったのは、朝鮮半島と軍事的緊張が高まったのが大きな要因である。
夫と妻は別々に埋葬されていたのである。
夫婦は血縁関係がないからだ。
妻は自分の出身地の陸陵で埋葬されたので、妻の両親・兄弟は同じ墓に入る。古代の結婚は同居を意味しない。戸籍も夫婦別姓であった。父兄社会では子供は父方の性を名乗る。別姓故に所有権・相続権が確保され、女性貴族(皇族)は女院と呼ばれ、妻が荘園を管理する例もあった。
妻に夫の親の相続権がないとするのは、血族中心の考え方で、家紋がその証拠である。家族の紋は三つある。夫の紋、妻の紋、夫の母親の紋で、男子は父の紋を継ぎ、女子は母親の紋を継ぎ、嫁いで夫の姓に変わっても母親の紋を継ぐ。妻の紋が入った衣類・道具は、妻の私有財産であり、離婚の際には財産分割の対象にはならない。
妻と夫と同じ紋であっても、女性の紋は男性の紋と異なり、紋に外輪がないので区別できる。
嫁入りには必ず「留袖」を母親が娘に持たせたが、現在は、レンタルでOKというのが一般的になってしまったので、女性の血族を表すものがない。
だから、夫婦別姓を主張する理由は、妻が実家の姓を名乗ることによって「女性の血族を表現したい」という表れなのではないかと思う。
そうなると、夫婦別姓を選んだ夫婦の間に出来た子は、男は父親、女は母親の姓を名乗ることになるのではないか。しかし、法的には何の根拠もない。
仮に裁判になったら、裁判所はどんな判決を出すのだろう。
夫婦別姓の議論が国会で取り上げられてから、世間でひと際注目されるようになった。今は、昔と違って専業主婦が少なくなり、女性活躍社会になったから、結婚して姓が変わるのを嫌う女性が増えてきた。
確かに最近の社会は女性活躍社会になったが、家庭では活躍しなくなったのではないか?
それだけではない!
最近は、死後離婚を望む女性が増えている。夫の墓に入りたくないという理由だけでなく、夫が亡くなり、夫の両親の面倒を見たくないという理由も少なからずあるそうだ。
真面目に考える必要はない!
離婚しなくても、夫の墓に入る法律上の義務はないし、夫の死後に多額の遺産が妻に入っても、その時点で死後離婚すれば姑の扶養義務はない。
夫の死後に復氏届を出せば旧姓に戻れる。旧姓に戻っても遺族年金は支給される。
結婚は一種の契約であるから、どちらの姓を名乗るのも、お互いに相談して決めればよい。契約は夫婦どちらかの死亡によって終了するから、死後離婚は契約者双方の権利である。夫婦別姓を望む人は、婚姻する際に必ず印鑑証明書を添付した契約書を作成する必要がある。そこには、生まれてくる子どもの姓、夫と姑との墓に同居しても良いか否か。姑から財産分与を受けた場合でも、死後離婚が可能とかを逐条にすることをお薦めする。どちらかが契約違反をした場合の罰則規定を定めておくのも重要だ。
尚、この契約書は、公正証書にしておくことが肝要。但し、気が変わればいつでも変更できる点は、遺言書と同じ。
一部のリベラリストは、こんなことを考えているのだろうか。
中山恭三(なかやま きょうぞう)/不動産鑑定士。1946年生まれ。
1976年に㈱総合鑑定調査設立。 現在は㈱総合鑑定調査 相談役。
著書に、不動産にまつわる短編『不思議な話』(文芸社)を2018年2月に出版した。