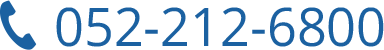3.コンパスの話
コンパスは、作成時に北を指す「磁針」は赤に塗られており、南を指す「磁針」は白になっている。「North」なのでNと表示されているため、地球の北側がN極と勘違いしている人が多い。北極側がN極だとしたら、コンパスのNはN極と反対の方向を向いていなければならない。磁石で経験された方は多いと思うが、NとN、SとSは反発するから、コンパスが北の方向を向いていたら必ずそこはS極でなければならない。
地球の内核は液体、外核は固体で、外核と内核の間の液体部分が回転しているから、磁力が作られ、S極とN極に分かれている。(ダイナモ理論)
地球は北極圏がS極、南極圏がN極とする大きな磁石である。
本来、北極は南極とし、南極は北極と呼べばこんな誤解はなかった。
しかし北にあるのに南極とは呼べなかった。そうしたらコンパスのNをSと表示しSをNと表示すればよかったのか。これも北が「SOUTH」になってしまう。う-ん、困った!
やはり北極はS極、南極はN極とするしかなかったか。
4.橋の話
ほとんどの人は気が付かないだろうが、橋には「入り口」と「出口」がある。
橋の名前が漢字で書かれている側は入り口、ひらがなで書かれている側は出口なのだそうだ。
入り口は、大きな町がある側で、同じ規模であれば北側か東側が橋の入り口になる。
入り口の橋の右側には河川名が書かれている。
出口では、橋の名前は「○○ばし」ではなく「○○はし」とひらがなで書いてある。濁点が付かないようにしたのは、川が濁らないようにとの配慮らしい。
そうすると、何故、川の名は「○○がわ」と濁点が付いているのだろう。
5.セブンティーンの話
集英社が出している「Seventeen」と言うタイトルの月刊誌があった。(2021年に月刊誌の発行は終了して現在季刊ごとに発行されている)これは17歳の年齢の人をタ-ゲットにしたものでなく、ティーンエイジャーの13歳から19歳までの少年・少女向けに販売されている雑誌。セブンティーンは17歳のことではなく、
- 13歳 サーティーン
- 14歳 フォーティーン
- 15歳 フィフティーン
- 16歳 シックスティーン
- 17歳 セブンティーン
- 18歳 エイティーン
- 19歳 ナインティーン
の7つ。知っていましたか? おじさんには関係ない?
6.「ふんどし」屋の話
江戸時代に貸し褌(ふんどし)屋があった。
何故こんな商売が成り立ったのか。江戸は単身赴任の武士が多く、武士が自分で褌を洗うことは沽券にかかわることである。このため、褌のレンタル業が流行った。
使い古された褌は別の業者に下取りされ、藍染めされて野良着にするか、赤ちゃんのオムツとして再利用された。藍染は繊維を強くするだけでなく、防菌・防虫効果があり、畑仕事ではマムシ除けにもなる。
最終的には、臼に入れてつくと繊維と藍の粒子に分かれ、繊維部分はボロ屋が引き取り、紙の屑を混ぜてちり紙や落とし紙として使われた。
藍の粒子部分は、ニカワと混ぜ「絵の具」として使った。
江戸時代は、物を大事にする精神があった。今は、その精神が失われてしまったのではないだろうか。
パンツを「再利用」するという話ではない。
7.エビ・タコ・イカは誤解されている
ある男女の会話。
“やっぱりフランス料理には「オマールエビ」が合うわよね”
“いや、俺は「ロブスター」がいいな。エビ自体にコクがあるからな”
隣のテ-ブルで聞いていた私は、これこそ勘違いの典型的な例だと思った。
「オマールエビ」と「ロブスター」は同じもの。オマールはフランス語、ロブスターは英語。
料理はフランス語の方がおいしそうに聞こえる。日本人はカタカナに弱い。
実は、「オマールエビ」、「ロブスター」より、伊勢エビの方が高級で値段も断然高い。
寿司屋でクルマエビを正式に書くと「車蝦」となる。中国では、蝦は「ガマ・ヒキガエル」等、カエルのことだから、中国人が寿司屋に入ると、ここはカエルの寿司を食べさせるのかとびっくりする。だから「海老」と書く。
エビには二種類ある。歩行型と遊泳型で、歩行型のエビは「海老」と書く。伊勢エビは代表的な歩行型なので、本来は伊勢海老と書く。
遊泳型は「蝦」と書き、代表的なのがクルマエビで、「車海老」ではなく「車蝦」が正解だが、何処の寿司屋さんも「車海老」と書いている。
恐らく中国人の客を意識して書いたものではなく、「蝦」の漢字をエビと読める人が少ないことを気にして「車海老」と書いたのか。或いは、寿司屋が知らなかったのか。何れにしても、間違った慣例が続いている。
「蝦」が虫編なのは、魚に区分されないものは、どれもこれも虫だと分類したためではないだろうか。
蛸(タコ)、蟹(カニ)以外に、貝類は虫に分類した。蛤(ハマグリ)、蜆(シジミ)、蚫(アワビ)。
海老の老は、ヒゲがあって、体が丸くなった老人に似ていることから、長寿を喜ぶ意味が込められているので「おせち」に使われる。
タコは本来、多股(足が多い)と書いたが、正式には足ではなくこれは腕。英語でもオクトパスは、オクト(8)、パス(足)で、足だと思っていたらしい。日本語では「蛸」と書くが、中国で蛸は蜘蛛(クモ)のこと。
蛸を食べると書く「飯蛸(イイダコ)」は、産卵期になると胴に卵が詰まって膨れるメス蛸で、この卵がご飯のようになるところから「飯蛸(イイダコ)」と呼ぶようになったらしい。
イカの墨は、メラニン色素の一種でマグネシウムとカリウムが含まれる塩類の化合物。昔、ローマ人が「コウイカ」の墨から作り、インキとして使われていた。
イカ墨はラテン語で「セピア」と言ったため、写真が古くなるとセピア色っていうのはここから来ている。
日本でも江戸時代に、借金の証文にイカの墨で書いたが、“返済期限が来たときに墨が消えて白紙になったため、証拠なし”として取り立て不能になったと奉行所が下した判決文があったという。実際には、イカの墨はTシャツについたら洗濯してもなかなか落ちない。この話は「イカサマではないか」。
イカを焼くと香ばしい匂いがするのは、「タウリン」と言う成分で、タコ、イカ、エビ、貝類に多く含まれるアミノ酸の一種。これは普通のアミノ酸と異なり、タンパク質を構成しないフリーのアミノ酸らしい。こんなアミノ酸があったとは驚きだ。
“「タウリン」1000㎎配合、リポビタンD”として宣伝されているタウリンは、胆汁の原材料になっているほか、コレステロールを掃除して血液の流れを良くする働きがある。
猫が鰹節を好んで食べるのは、このタウリンを補うためらしい。
タウリンが欠乏した猫は、暗闇でネズミを取れなくなってしまう。しかし、今どきの猫はタウリンの欠乏に関係なく、明るいときでもネズミは取らない。それどころかネズミを見て逃げてしまう。
スルメを焼くと丸くなるのは、イカの筋肉がリング状に回っているから縦には裂けない。
皮が熱によって引っ張られ、皮のある側にまるまるからで、焼く前に皮に軽く切り込みをつけると丸くならない。
イカは「烏賊」と書く。イカが死んだふりをして水面に漂い、これを捕ろうと舞い降りた鳥を、逆に捕まえて食べたと言う中国の伝説によるものだが、イカが鳥を食べる様子を見たものは誰もいない。この話も「イカサマ」ではないか。
“ある日、海岸でイカが昼寝をしていた。そこにサルがやってきてイカの足を一本食べてしまった。びっくりしたイカは、沖の方に逃げて手を振りながらこう言った。
「おサルさ-ん!こっちへおいでよ。まだ残っているから食べにおいでよ!」と大きく手を振った。
サルは言った。“その手は桑名(喰わな)の焼き蛤!”
イカの10本の足は足ではなく、サルが言うように「手」即ち「腕」だった。
タコも同じで、頭の付け根から腕が出ている。
頭の付け根から足が出ている生物はこの世にはいない。
中山恭三(なかやま きょうぞう)/不動産鑑定士。1946年生まれ。
1976年に㈱総合鑑定調査設立。 現在は㈱総合鑑定調査 相談役。
著書に、不動産にまつわる短編『不思議な話』(文芸社)を2018年2月に出版した。